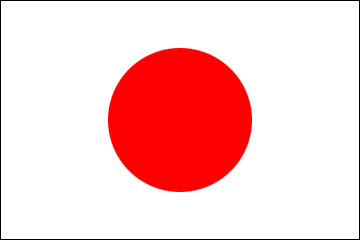在留証明
令和5年12月15日
概要
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去にどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(カナダ国内に限ります):形式2)、又は同居している家族(現住所及び同居家族の証明:形式2)を証明するものです。使用目的
日本における恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、学校の受験手続や免税購入に使われます。
申請に当たっては、提出先によって、求める滞在期間や本籍地の市区郡以下の記載が必要かどうか異なりますので、事前に提出先にご確認の上、必要書類をご準備ください。
*1 免税購入の必要書類は「戸籍の附票の写し」でも代用可能です(詳細はこちら)。
*2 日本年金機構、公立学校共済組合の年金受給手続きにおいては、大使館・総領事館発行の「在留証明」の代わりに居住国の公証人のサイン入り証明で代用可能と説明されています。公証人による証明を希望する場合、当該機関からの通知に従い、英文の「Application for Residence Certificate」を記入するか、ご自身で英文にて作成後、Notary Public(公証人役場)にて公証を受けたもの(機関によっては和訳文も添付)を現況届等必要書類とともに日本側関係機関に提出してください。なお、詳細については提出先にご相談ください。
在留証明を申請できる方
日本に住民票がなく、日本国籍を持ち、当館管轄地域(オンタリオ州オタワ市内)にお住まいの方必要書類(すべて原本。電子データが原本である場合、印刷したものも併せてご持参ください。)
- 申請書(当館に備え付け有り)
- 有効な日本のパスポート
- 当地滞在資格を証明するもの(Permanent Resident (PR) Card, Work Permit, Study Permit 等)
- 住所を立証できる文書(オンタリオ州の運転免許証、公共料金の請求書又は領収書等)
- 滞在期間を確認出来る文書(公共料金の請求書又は領収書、不動産売買契約書等)
「住所(又は居所)を定めた年月日」の記載を必要としない場合には不要です。免税購入が目的の場合、形式1または形式2を問わず2年以上引き続きカナダ国内に居住していることを証明できることが条件となります。「住所(又は居所)を定めた年月日」欄は提示された文書を確認の上、窓口で記入いたします。 - 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類(免税購入を目的とする場合は必ずご用意ください。年金受給などの目的で本籍地の「市区郡以下」の記入を必要としない場合は不要です。)
- 恩給・年金受給手続の場合、受給を証明するもの(受給証書等)
- 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する文書(4及び5参照)等
- 同居家族を証明する場合、申請者及び証明対象となる御家族の方全員のパスポート、当地滞在資格及び住所・在住期間を証明する文書(同居家族の証明に限り、同居家族宛で消印のある郵便物も可)※在留証明対象となる同居家族は日本国籍に限ります。
手数料
支払い方法は現金のみ。料金表はこちら。*次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。
- 恩給
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
- 国民年金
- 厚生年金(平成27年10月1日から公務員及び私学教職員等が加入する共済年金は厚生年金に統合されました。)
- 船員保険年金
- 労働者災害補償保険年金
注意事項
- 免税目的の在留証明については、こちらもご参照願います。
- 令和6年度4月1日から法改正により、不動産を相続した場合、相続登記の申請が義務化されます。日本国外に居住されている方も対象となります。詳細はこちらの法務省ウェブサイトをご確認ください。
- 代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。
- 「形式2」を申請して過去の住所を証明する場合、現在の住所に加え、過去の住所地及び在住期間を立証する書類の提出が必要です。なお、過去の住所地の証明はカナダ国内に限られます。
- 過去の各住所地及び在住期間の証明書類は、書類の日付、住所地、氏名が記載されている項・箇所が容易に確認できるよう事前にマーカーや付箋等で印を付け、窓口担当者に示してください。
- 「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄は、申請時にご提示いただく在住期間を立証する公文書等に基づいて当館で記入します。
家屋の契約書で、入居日が2000年5月20日の場合:2000年5月から居住
公共料金の領収書等の日付が2000年11月3日の場合:2000年11月から居住
- 証明書は戸籍謄(抄)本どおりに氏名、本籍地(特段の必要がなければ旅券に記載されている都道府県名)、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので、事前にご確認ください。 なお、本籍地の記載は、提出理由が免税購入の場合は必要(免税購入は戸籍の附票の写しでも代用可能です。詳細はこちら)ですが、恩給・年金受給手続の場合は不要です。
- 日本国籍を喪失された方、外国籍の方は当地公証人により証明を受けてください。
- 帰国後に、年金受給手続を行う方やお子様が帰国子女枠などでの受験を考えている方は、帰国や転居前に取得されることをお勧めします。